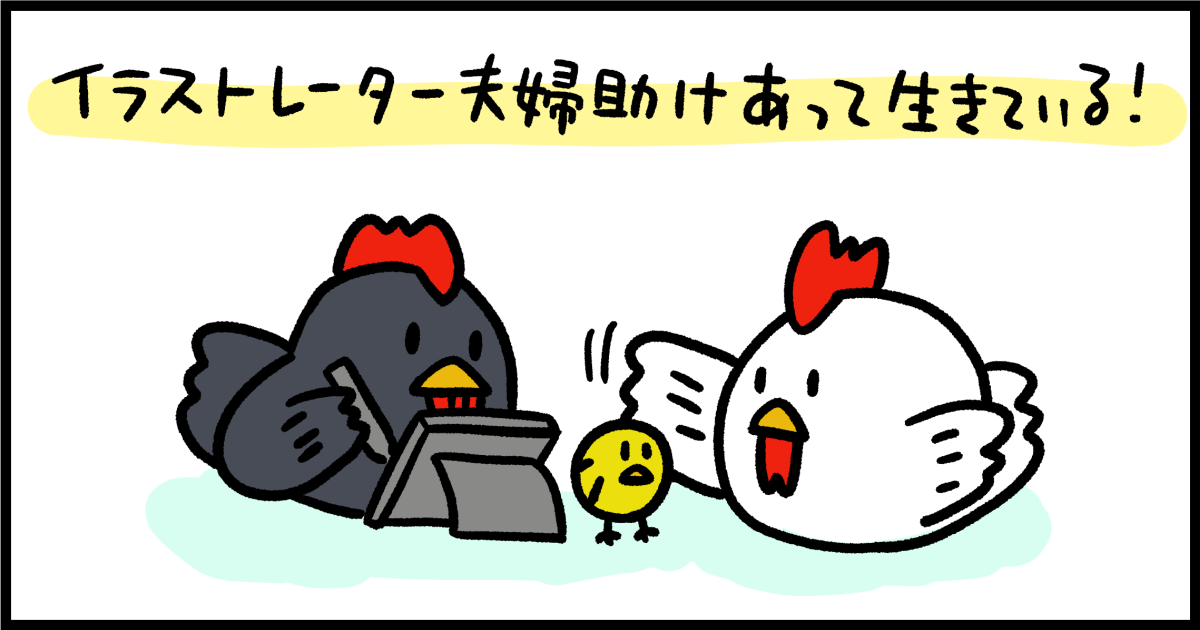「バズる才能」がなければ「バズらない才能」に目を向けて。絵描きとしての居場所の探し方
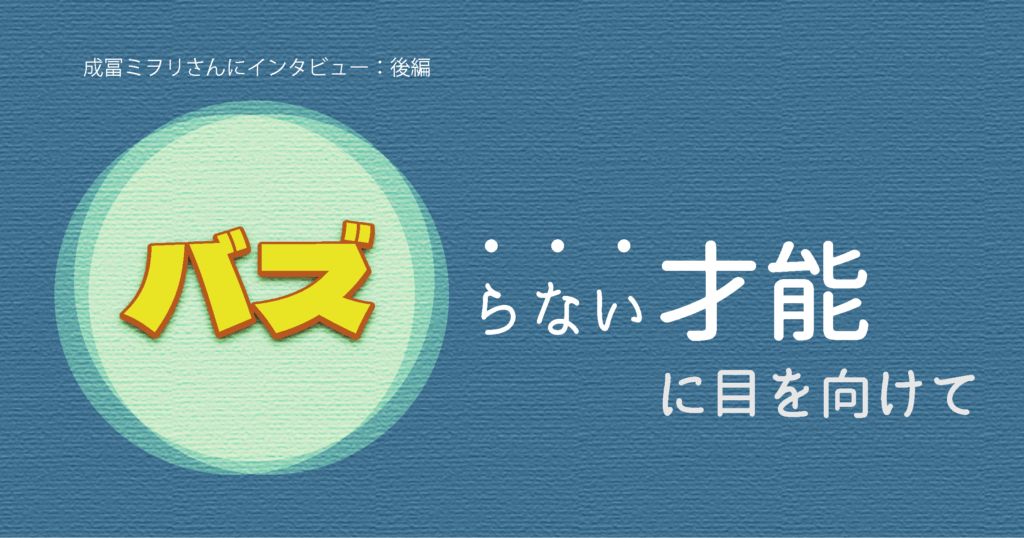
自分自身の「好き」を掘り下げて、コントロールできるようにする――成冨さんは、絵の技術やテクニックよりも、まず自分について知ることが、絵を長く続ける秘訣だと話します。
後編でうかがうのは、「絵描きとしての居場所の見つけ方」について。まずは成冨さんが絵の仕事をするようになった経緯から、そのヒントを探ります。
お話を聞いた人

成冨ミヲリ(X:@naritomi/Web)
デザイナー・CGアニメーター・シンガー・文筆業。東京芸術大学美術学部工芸科卒。学生時代より集英社などのCM絵コンテを手掛ける。卒業後、ゲーム会社(3DCG、ドッター)、コンテンツ制作会社(アニメーション制作)を経て独立。フリーランスで活動後、2002年に有限会社トライトーンを設立。主にアニメーションの制作を行ったのち、エンターテ インメントを中心としたデザインを手がけるようになる。また、プロ向けのデッサンスクールを設立、3,000人を超えるクリエイター に絵を教えてきた。また、ゲーム制作会社等の研修などを通じてコンテンツ制作業界のレベル向上に貢献している。
(聞き手:ヒガキユウカ)
自分が得意だと思っていた絵は、美大では通用しなかった
――後編では、成冨さん自身のご経験もうかがっていきたいと思います。成冨さんは、絵が好きで美大に進学したのでしょうか?
成冨
純粋な好きというより、「得意」が近かったですね。もっとも「得意だから好き」はありました。数学が得意な人が理系に進もうと考えるのに似ていると思います。
それで美大を目指したんですが、高校は進学校だったので、まわりはみんな普通大学を目指して受験勉強をしていて。「好きなことが見つかってる人はいいね」「絵描いてればいいんだもんね」と言われていました。
――人と違う道に進むことが、皮肉の対象になってしまう時代だったんですね。
成冨
そうですね。でも第一志望だった東京藝術大学の入試は、デッサン7時間、色面構成6時間、立体6時間、それに加えてセンター3科目がありました。高2から予備校に通っていたんですが、高校生では間に合わない量の実技課題と学科の勉強があって、内心では「普通の学科だけの入試の方がよっぽど楽じゃん」と思っていました。
課題の絵も、順位を付けられてその順番に並び替えられたりするんです。そんな環境だから、絵が好きかと言われると正直わからなかったですね。泣いてしまう子や病んじゃって来なくなる子もたくさんいました。みなさんがする受験勉強と同じように、必死で技術の会得をしている感じでした。
――そうして、東京藝術大学に見事現役で合格されます。入学後はいかがでしたか?
成冨
入った後は、別の意味でものすごく大変でした。当時は平均三浪と言われる世界で、現役はクラスにひとりかふたりしかいなくて。何年もデッサンだけやり続けた人なんかもいるから、自分の経験値では到底ついていけないんです。ずっと自分の居場所がないような気がして、大学での4年間は暗黒時代でしたね。自分の才能のなさを認めるのはきつかったです。

うまくなくてもいい。コンビニバイトのポップ描きの経験に救われた
――美大で絶望を経験した成冨さんは、どこで絵描きとしての居場所を見つけたのでしょうか?
成冨
当時、美大に通いながらコンビニでバイトをしていたんですよ。そこで「ポップを描いて」と頼まれて、小さな紙にお菓子の宣伝を描いたら、すごく売れたんです。コンビニって誤発注で多く仕入れ過ぎてしまうことがあるんですけど、それもイラスト入りのポップを添えると飛ぶように売れるんですよね。
そうしたら本社の人が来て、「他の店舗の分も描いてほしい」と言われて。バックヤードで時給をもらって、あちこちのポップを描くようになったんです。そのうち売り場のディスプレイも作るようになりました。大学だとまわりについていけないぐらい下手だったのに、一歩外に出ると、絵が描ける人としてみんながチヤホヤしてくれたんですよね。
またあるときは社会人の先輩に頼まれて、CMのセットに絵を描く仕事をしました。現場に絵の具を持って行って描いていたら「あなた絵描けるんだね」「絵コンテって描ける?」と話しかけられて、「描けると思います」と言ったら、一枚5,000円で絵コンテを描く仕事が始まりました。
――大学ではしんどかったけれども、外に出てみたら、仕事が仕事を呼んでいったんですね。
成冨
そうです。そのときに大事なのは、「私は絵が描ける」ということだけでした。その絵がうまいかどうかとか、学歴がどうかといったことは、みんなあまり気にしていないんです。仕事が始まってから、取引先に「そういえば専門学校出身なの?」と聞かれることもありました。
誰かにとっての「身近にいる絵が描ける人」になるだけで、案外仕事としてやっていけるんだなと思いましたね。そのスタンスのまま、営業せずずっとここまで来ています。
絵の仕事とは、誰かの困りごとを絵で解決すること
成冨
仕事とは、何かを担うことだと私は思っています。例えば無地の洋服に小さな花の絵があったら、アクセントになりますよね。ペットボトルのお茶には、おいしそうに見えるためのパッケージデザインが必要です。家電の取扱説明書には図解が必要だし、漫画の世界では背景だけを担当するアシスタントもいます。
その視点で世の中を見てみて、自分ならどれを担えるかを考えてみる。絵の仕事って、すごい作品をつくるとか、すごく絵がうまくなることじゃなくて、「そこに絵がなくて困っている人の悩みを解決すること」なんです。その意味では、コンビニでポップを描いていた大学生の私も、いろんな企業をお手伝いしている今の私も、やっていることは同じだと言えます。
――ある有名なイラストレーターにインタビューしたとき、「今ここにポスターがあったとして、そこに絵がないよりある方が良いでしょう? 絵がうまいか下手かより、必要な絵があるかないかで考えてください」という話をしていたのを思い出しました。
成冨
まさに、そういうことだと思います。絵で仕事をしていきたいなら、うまいか下手かはどうでも良いとすら私は思っています。「いつか絵がうまくなったら仕事にしよう」だと、時間だけがどんどん過ぎていってしまいますから。
自分が今持っている武器がひのきの棒だけだったとしたら、そのひのきの棒でできることをするしかないですよね。伝説の剣を持った人は派手な必殺技を打てるかもしれないけど、まわりの弱い敵を減らしていく人だって必要なはず。それが自分の居場所です。
仕事においては、絵が描けるのは当たり前で、その上で「何が得意で何が描けるの?」という話から始まります。そこで改めて、食べるのが好きだから料理のイラストが良さそうとか、スポーツが好きだからスポーツ関係の仕事ができそう、と発想していくイメージです。
――普段は絵そのものばかりに意識が向いてしまいますが、改めてまわりを見渡してみると、生活の中で絵が必要なポイントってすごくたくさんあるんですね。
成冨
そう思える人は、もうスタートラインに立っていると思います。私もそうでしたが、好きかどうかとか、才能があるかどうかで悩んでしまうと、視野も狭くなってしまう。絵が目的になってしまうと難しいので、あくまで誰かの困りごとを自分の「好き」で解決するのが仕事。絵はその手段にすぎない、という意識が大事だと思います。
少数に深く刺す「バズらない才能」に目を向けて
――成冨さんの駆け出しのころと今で大きく違うのが、SNSがあることだと思います。SNSに居場所を求めるあまり、リアクションの数が気になってしまう人も多いと思うのですが、どういうふうに付き合っていけば良いと思いますか?
成冨
SNSには、フォロワー数が順調に増えていって、絵も着実にうまくなって、どんどん知名度が上がっていくという人もいます。そういう人を見ていると、そのやり方が正しいように見えますよね。実際、これはひとつの才能です。世間のニーズをしっかり捉えて、たくさんの人の目に留まる才能があると言えます。
じゃあ伸びない人たちに才能がないかというと、そんなことはありません。王道の人が取りこぼした、少数の人たちにアプローチするクリエイターも必要で、これも同じく才能です。売れている人は目に入る機会も多いので、「そうなれない自分はダメなんじゃないか」と思いがちですけどね。バズる才能があるなら、バズらない才能もある。ニッチなジャンルに居場所を求めるのも、ひとつの生存戦略ですよね。
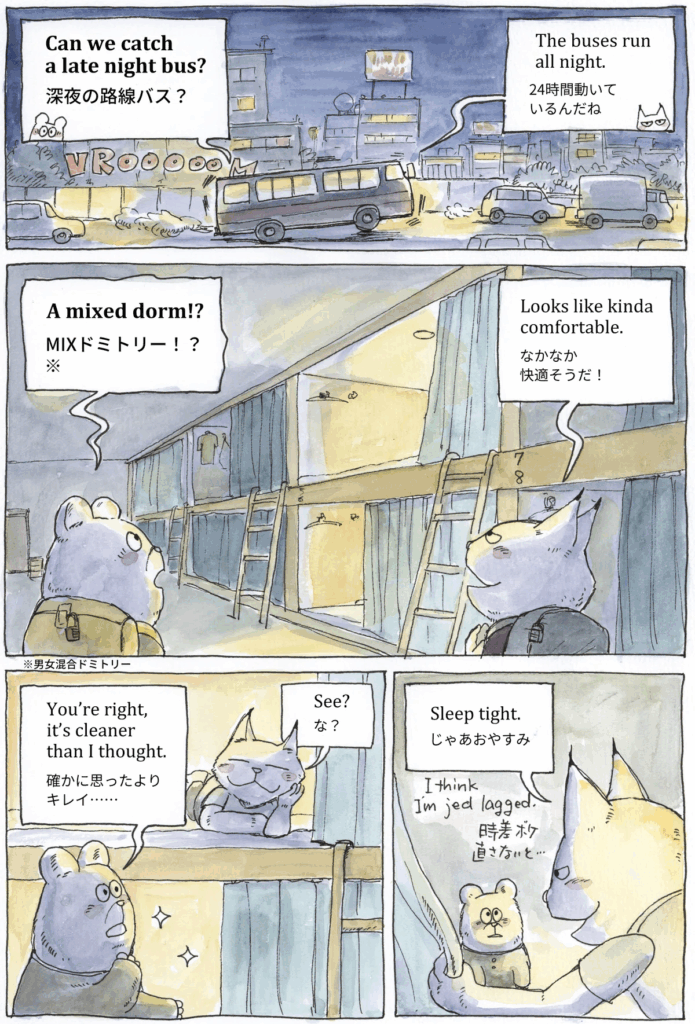
――「自分はバズらない方の人間だ」と思ったら、どこを意識して絵を描けば良いでしょうか?
成冨
そうですね。例えば私がスクールで生徒さんを見るときは、まず「その人の才能がどこにあるか」を考えます。
――才能は誰にでもある前提で考える、と。
成冨
前提も何も、才能は誰にでもあるんですよ。すべてにおいて優秀な人はなかなかいない代わりに、誰しも何かには秀でています。
生徒さんに対しても、絵がうまいかどうかは見ていません。「そのジャンルの絵はあわないね」と判断することはありますが、同時に「じゃあ何が描けそうかな?」と考えていきます。極論、「絵は人並みだけど、アイデアがたくさん出せるんだね」という結論に至ることもあります。でもアイデアが出せて人並みに絵が描ければ、仕事にはなりますよ。
――好きに種類があるように、絵のうまさも細分化できそうですね。
成冨
絵の才能がある・ないとか、バズる・バズらないとか、昨今は何かと二元論になりがちですよね。本当はもっと複雑なものだと思います。
例えば立体で把握する才能と平面で把握する才能は別物だし、適した仕事も全然違うはずなんです。
好きなものや得意なもの、生い立ち、育った環境や宗教、すべてがその人のパーツなんです。その中で自分は絵が描けて、この場所には絵が足りない。それが見えたときに、自分の担う場所がわかってくると思います。
インタビュー・執筆
ヒガキユウカ(X:@hi_ko1208)
この記事を読んだ人におすすめの記事
-
2022.10.4
-
2023.10.31
-
2022.7.26
-
2022.9.21
きっかけは育休中にSNSで見たコピックイラスト。育児と仕事も両立しながら、描き始めてたった4年でフォロワー2万超えの兼業イラストレーター・彩木ぴすこの素顔
-
2023.3.8
-
2025.7.8