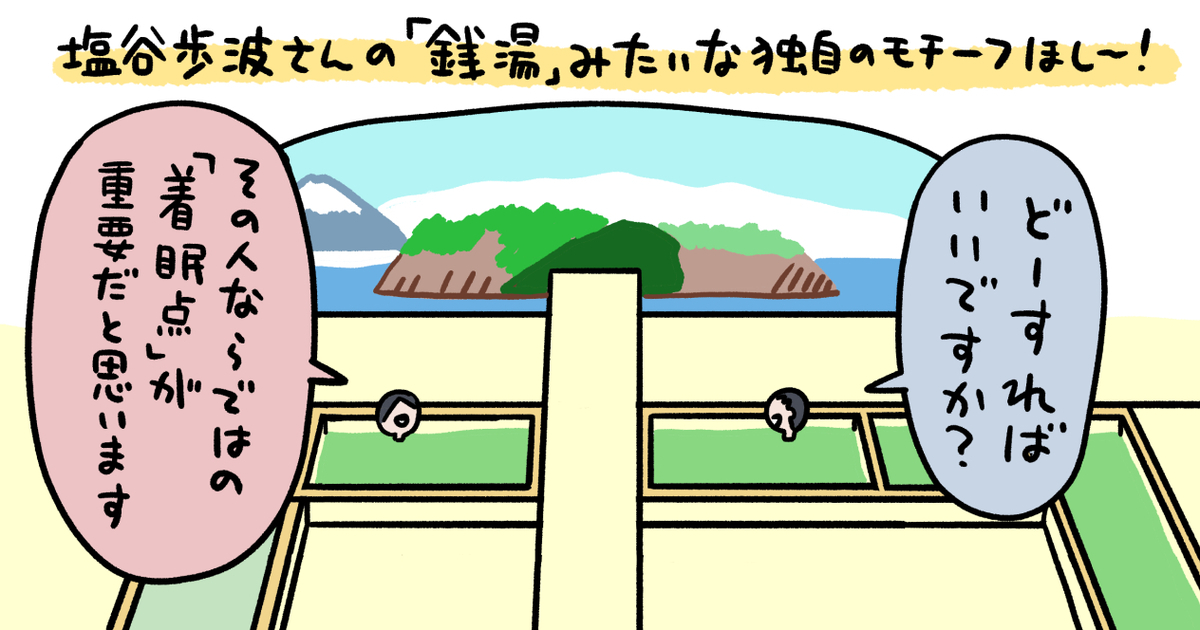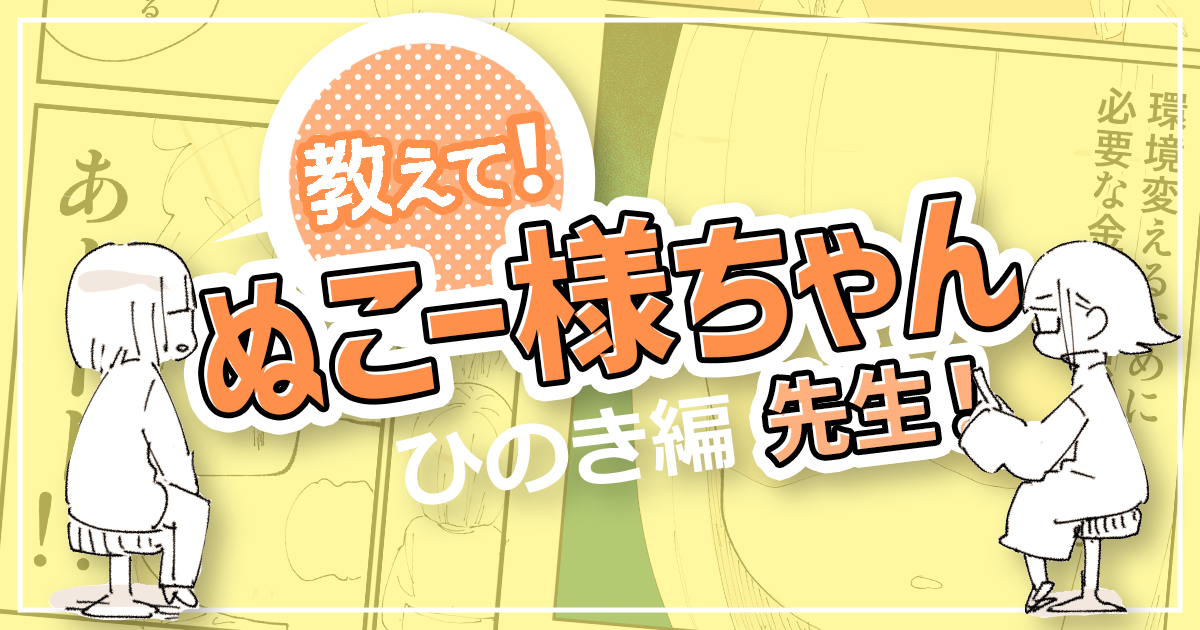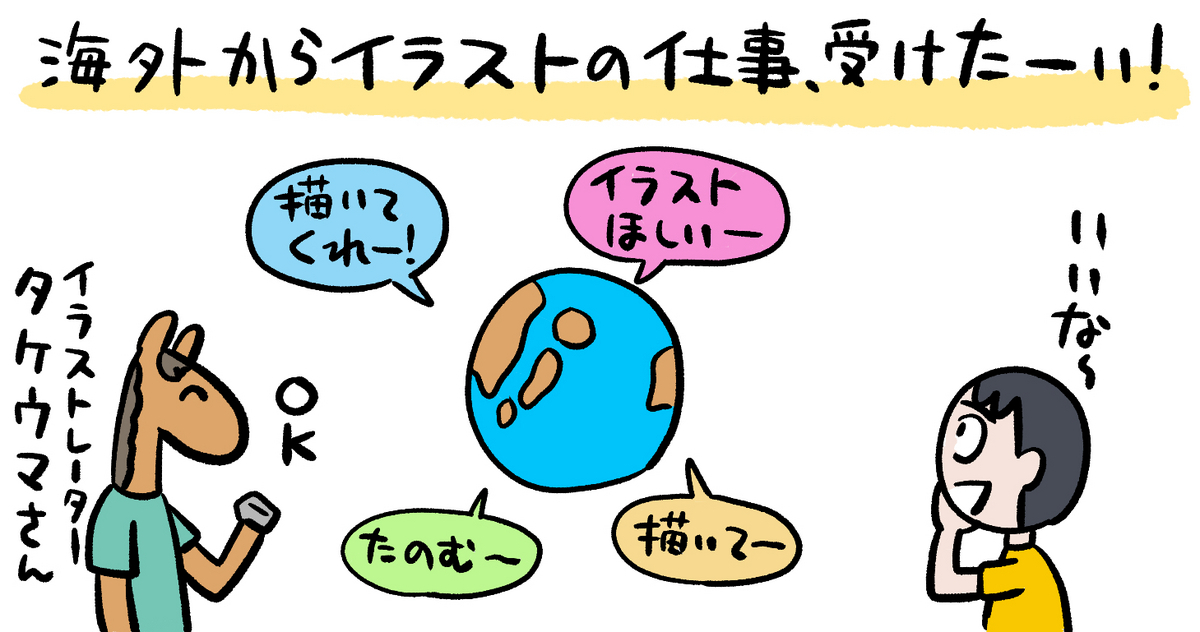「絵がうまければ漫画家になれますか?」 カメントツ先生に聞く【漫画お仕事道】第1回
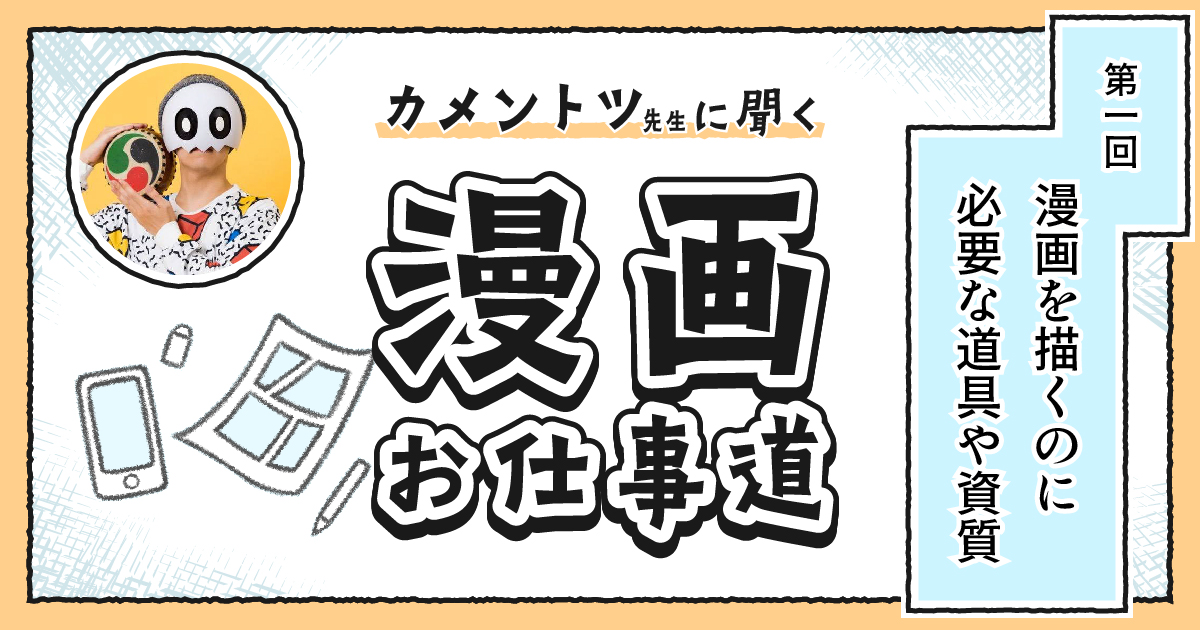
「漫画を仕事にしたいけど、どうしたらいいかわからない……」そんな悩みを持っている人はいませんか。
この連載では、『こぐまのケーキ屋さん』などで知られる大人気漫画家のカメントツ先生に「漫画をお仕事にするために必要なことについての質問」に答えていただきました。
今回のテーマは「漫画を描くのに必要な道具や資質」です。第一線で活躍するプロの知見、ぜひ参考にしてください!
第1回「漫画を描くのに必要な道具や資質」(この記事)
第2回「漫画を描きだしてからの悩み」
第3回「デビューするにはどうしたらいいのか」
第4回「SNSや収入など漫画家Q&A」
答えてくれた人
カメントツ(X:@Computerozi)
漫画家。愛知県出身。2015年より『オモコロ』にて漫画家の活動をスタート。2017年にTwitter(現X)で発表した『こぐまのケーキ屋さん』が大ヒット。
Q.漫画を描くために必要な道具はなんですか?
A.まずは自分の手元にあるスマホやコピー紙、なんでもいいから使って描いてみよう。描きながら必要になったらステップアップしていけばいい。
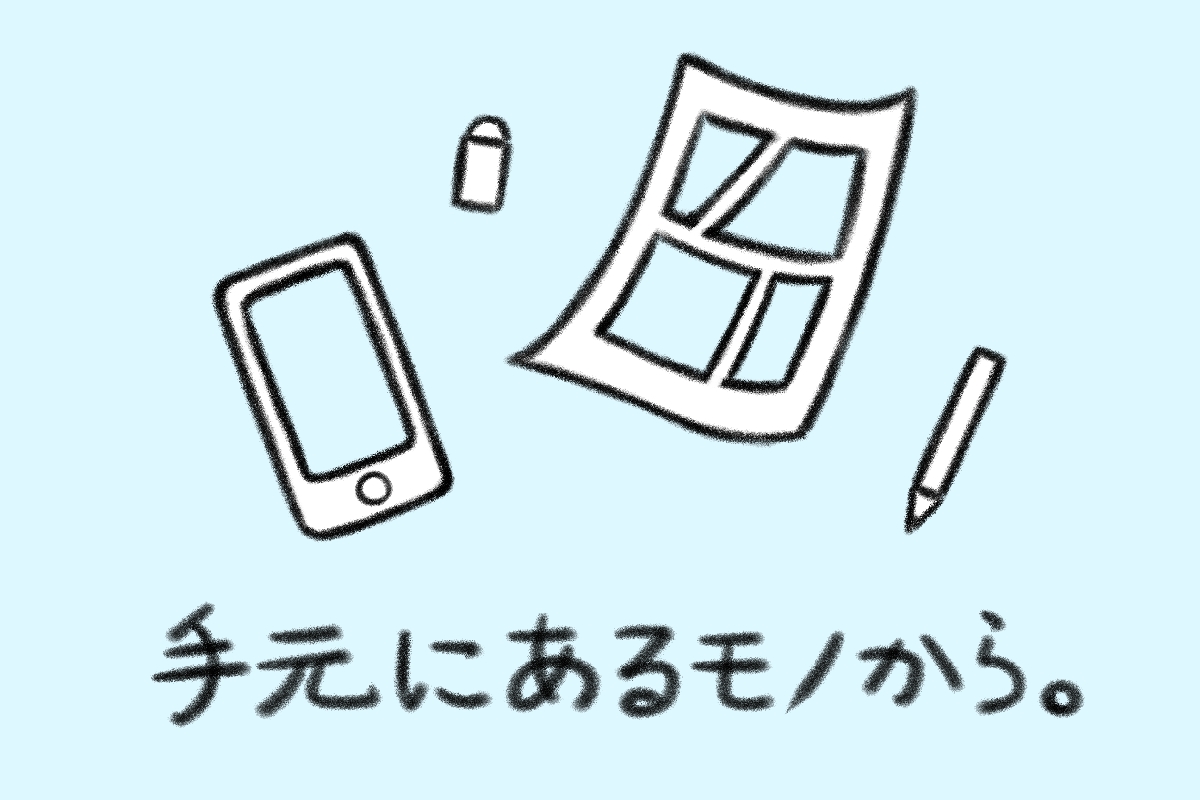
ーーすごく初歩的な質問なんですが、漫画を描くために必要な道具を教えてください。
カメントツ先生
スマホがあれば問題なく漫画は描けると思います。最初から液タブや板タブが必須とは、僕は思いません。
実際に僕が見た中でも「全部スマホで描きました」という人もいて、それで新人賞をとった人もいますね。特にデビューの年齢が比較的若い傾向にある少女漫画系には、顕著だと感じています。「スマホで描けるの?」って人もいるかもしれませんが、スマホってものすごく高機能なんです。
まず、好きな紙に自分の好きなペンで描きます。これは本当になんでもよくて、極端な話、チラシの裏に鉛筆でもかまいません。裏写りしてるのが逆に味になるし、実際にそれを効果として使った漫画家さんも実際にいます(こうの史代先生の『古い女』」)。
それをiPhoneのスキャンアプリで取り込みます。このときに「モノクロ二階調」というモードにすれば、白と黒のみの画像になります。漫画制作アプリを使えば、コマ割りや、トーン貼り、フォントを入れることもできます。
ある程度以上のスペックのスマホであれば、白黒漫画が入稿可能な600dpiのデータも軽々と扱えますし、CLIP STUDIO PAINTも開けます。iPhoneのLiDARを使えば、周りにあるものを3Dスキャンすることもできます。
だからスマホさえあれば、執筆から取り込み、入稿までできちゃうんです。そうした機能を使いこなしていない人がほとんどです。
「ペンタブ、液タブが無ければ漫画が描けない」と思っている人はまず手元のスマホのポテンシャルを引き出してください。その後に、目的に応じて道具をアップデートしていく形がいいと思います。
ーー特別な道具を使うのではなく、まずは自分の持っているもので描いてみるんですね。
カメントツ先生
有名な話ですが『サザエさん』作者の長谷川町子先生が「旅先で急遽1本漫画を描かなきゃいけなかったから文房具屋で紙とペンを買ってその場で描いて郵送した」とエッセイで書かれていました。
漫画家って、どこにでもありふれたもので仕事をするものなんだと、印象に残っています。長谷川町子先生の時代はそれが紙とペンでしたが、今ではそれがスマホだろうと思うんです。
Q.絵がうまければ、漫画家になれますか?
A.単純に絵が描けるだけでは難しい。おもしろさを読者に伝える構成力が必要。
ーー漫画って、絵とストーリーの両方が必要ですよね。それでも、やっぱりうまい絵が描ける人が漫画家になっているように思います。絵がうまければ、漫画家になれますか?
カメントツ先生
そもそも「漫画とは何か?」ということをここでまず一度考えてみましょう。漫画とは「さまざまな情報」を、コマ割りを使って読者に理解しやすい形で表現するものだと、僕は考えています。
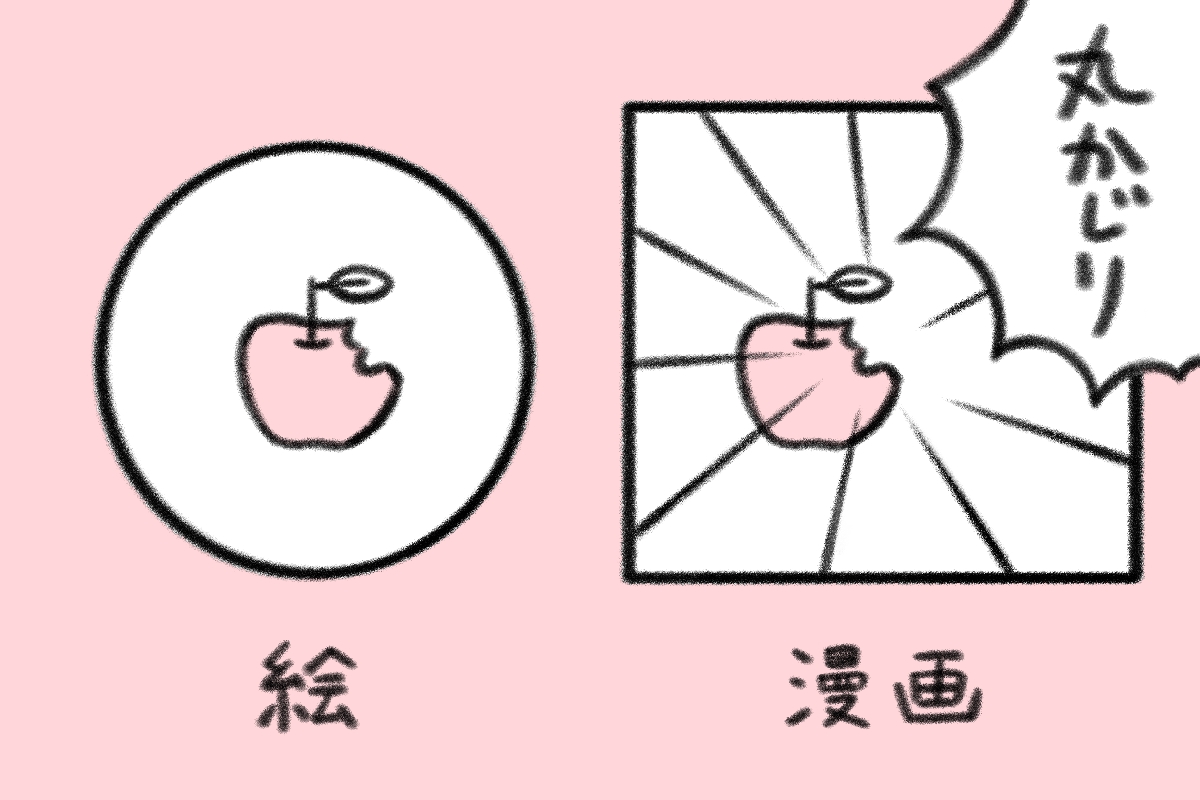
いま「さまざまな情報」と言いましたが、これはストーリーだったり、キャラクターだったり、単に文字情報だったり、いろいろなものが考えられます。このときに重要なのは、そもそもの情報が持っているおもしろさを読者にきちんと伝えることです。
ーーそう考えると、漫画家にとって画力ってそこまで重要ではないのでしょうか?
カメントツ先生
単純に絵が描けるだけでは、漫画を仕事にしていくのは難しいように思います。「作画と作話を分業しているケースもあるじゃないか」と思う人もいるかもしれませんが、そもそもプロで作画を担当されている漫画家さんはめちゃくちゃ構成力や想像力がある方が多いです。
できないことを分業で補っているのではなく、もともと強いガンダムに色々と強化パーツをつけてパーフェクトガンダムにしているんです。絵のうまさだけでやっていこうと思っている人は「自分はガンダムか?」と少し立ち止まって考える必要があるでしょう。
仕事として漫画を描くなら、絵のうまさ以上に情報をうまく読者に伝える構成力が求められます。テーマや切り口がユニークであれば読者は興味を持つし、伝え方によって漫画のおもしろみも変わってきます。
Q.漫画家として「読者に伝える」能力って、どうやって磨けばいいですか?
A.はじめて漫画を描く人はとにかく設定を詰め込みすぎて失敗しがち。まずは短いページで漫画のネームを作ってみよう。
ーーそうした構成力は、どのように磨けばいいのでしょう?
カメントツ先生
短いページでネームを切って漫画を作る練習をするといいでしょう。大学の講師として学生に漫画の授業をすることがあるんですが、まず4ページくらいの短い漫画を描いてもらっています。
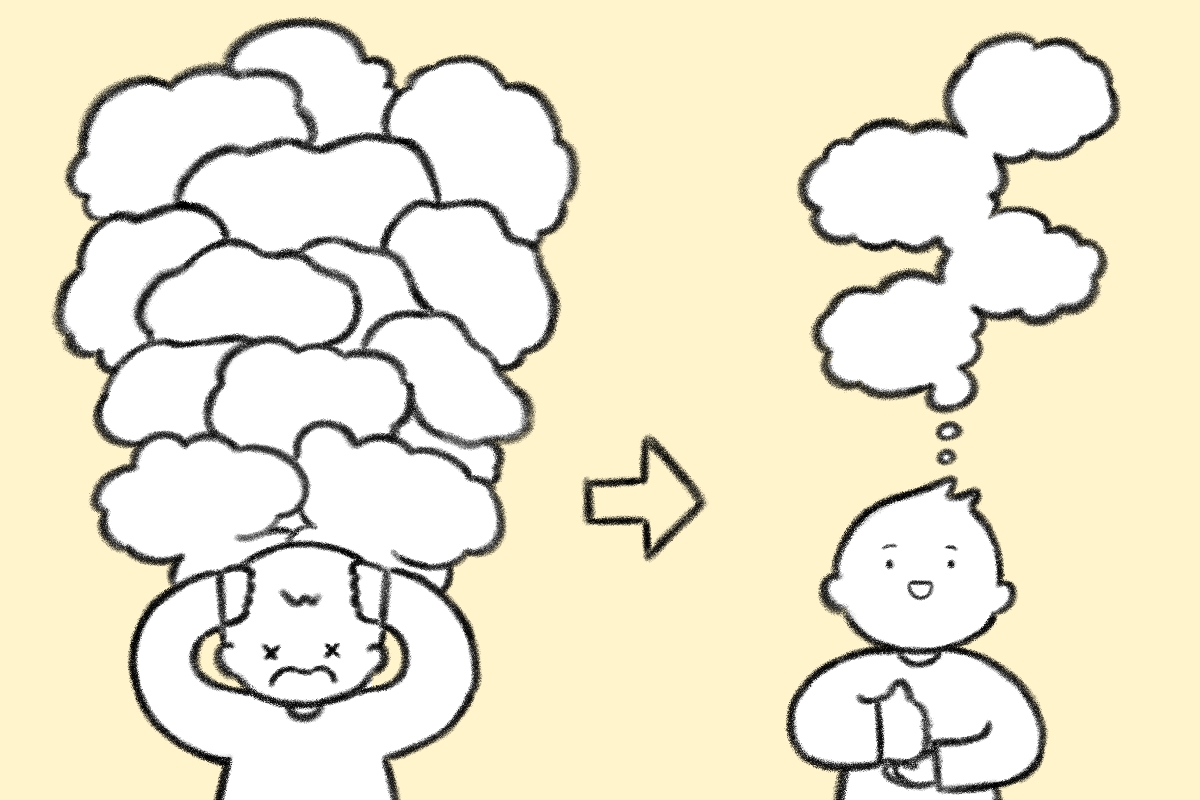
このときに、1ページ目から「〇〇帝国は滅びた……」とか「無限に広がる大宇宙から〇〇が……」とかスケールの大きい話をしちゃうと、絶対4ページには収まりませんよね。
はじめて漫画を描く人はこんなふうに、最初に設定を詰め込みすぎて失敗しがちです。デビューできない典型例でもあります。「せっかく描くのだから1作でアイデアの全てを表現したい」と思う気持ちもわからなくはないのですが、それはかなり非効率な願望だと思います。
ーーこうした場合は、どうすればいいのでしょうか?
カメントツ先生
テクニックの一つとして設定の説明を省略するために、説明の必要がないくらい、みんなが知っているキャラクターを使ってしまうという手があります。
例えば、「怪物を討伐して故郷に帰った勇者が、逆に人間から怪物扱いされて悲しい」というあらすじの作品を描くとします。
過去に勇者がどこで生まれたのか、どんなモンスターと戦ったか、どんな仲間がいたのか、説明し出したら膨大なページが必要となるかもしれません。
しかし、この物語の主人公を”桃太郎”のような童話をモチーフにする。すると「鬼ヶ島から桃太郎が帰って来たぞ!」とすれば最短で説明が済みます。このように読者に前提情報を伝える手間が省略できる方法はいくつもあります。
ーーみんなが知っている童話を使っちゃうんですね。ちょっとズルいような。
カメントツ先生
バレて困るのがパクリ、バレないと困るのがパロディ、バレても構わないのがオマージュ……と擦られ続けた名言があります。大丈夫。むしろ自分の実力もわからず完璧なオリジナルを目指すのは無理ゲーです。
それに漫画家には、自分の実力を見積もって、ページ数や締め切りから逆算してどれだけのコストをかけられるかの計算力も必要になります。
今ある状況の中で、「自分になにができるか」をしっかり考えられる人は、漫画家としての地力があると思います。
残りのページでこの物語をどうまとめるか、まとめられないなら違うものにするのか、なんとかアイデアを出して描き上げるのか……など、漫画家はジャッジの連続です。そうした決断力も漫画家に必要だと思います。
Q.絵と ストーリー、どちらを先に作ればいいですか?
A.絵とストーリーは切り分けられないので同時進行で考えてみて。行き詰まったら、臨機応変に試してみよう。
ーー実際に漫画を描こうとしたのですが、絵とストーリー、どちらから進めたらいいのか迷ってしまいました。なにかコツはありますか?
カメントツ先生
「人それぞれ」という言い方をすると何も答えになっていないですよね。うーむ。
業界では、ネーム作業から始める……というのが通例です。
ネームとは、漫画の構成、ストーリー、後に何を作画するか……などのある程度の方向性を決める「下書きの下書き」のような作業です。
しかし、ネームを絵から描いているか、物語から書いているか?と聞かれると困ってしまいますね。まるで「走り出すときに足と手どっちから動かすか?」と聞かれているような気持ちです。
ーー決まったルールはないのですね。ネーム作業に失敗するケースとしてどんなものがありますか?
カメントツ先生
まず多いのがネーム作業の段階から絵に根を詰めすぎるタイプです。次第に絵を無理やりストーリーに当てはめるような形になり、辻褄合わせが物語を作る段階で発生してしまい、全体の調和が取れなくなって失敗する、ということがあります。
その一方で、ストーリーを先に決めた方がいいとも言い切れません。漫画を描いていると発生するグルーヴ感や作者の思ってもいなかった登場人物の動きが漫画をグッと良くすることがあります。
展開にバッファのようなものを担保しておくのが大切です。そのためにもあえてあいまいにしておいた方がいい。
例えば、漫画を描いていく中で「一見優しそうなキャラクターが実はヤバいやつだった」という意外な展開が自然と生まれることってあると思うんです。
漫画家が一番近い場所で物語を楽しむ事ができればいい。そうなってくると、絵とキャラクターがストーリーに引っ張られることもありますし、その逆もあります。そう考えると、やっぱり絵とストーリーは同時進行で考えていくことが必要だと思います。簡単に分けられるものでもないかと。
ここは人によって得意なスタイルがあると思うので、自分に最適な方法を、臨機応変に試してみることをおすすめします。
「人による」「工夫次第」ってね……。アドバイスにパンチがなくて恐縮ですが、広域で普遍的なアドバイスってそんなもんかもしれませんね。
むしろ「◯◯するだけでうまくいく」のような情報が氾濫してて、ゴニョゴニョゴニョ……
第1回「漫画を描くのに必要な道具や資質」(この記事)
第2回「漫画を描きだしてからの悩み」
第3回「デビューするにはどうしたらいいのか」
第4回「SNSや収入など漫画家Q&A」
執筆
神田匠(X:@gogonocoda)
イラスト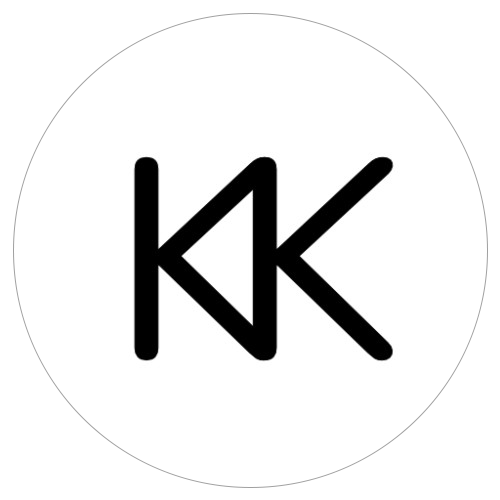
穀物かじつ(GENSEKI/X:@k_kajitsu)
この記事を読んだ人におすすめの記事
-
2023.12.6
-
2022.6.13
-
2024.8.1
-
2023.1.18
-
2024.5.1
-
2024.6.27