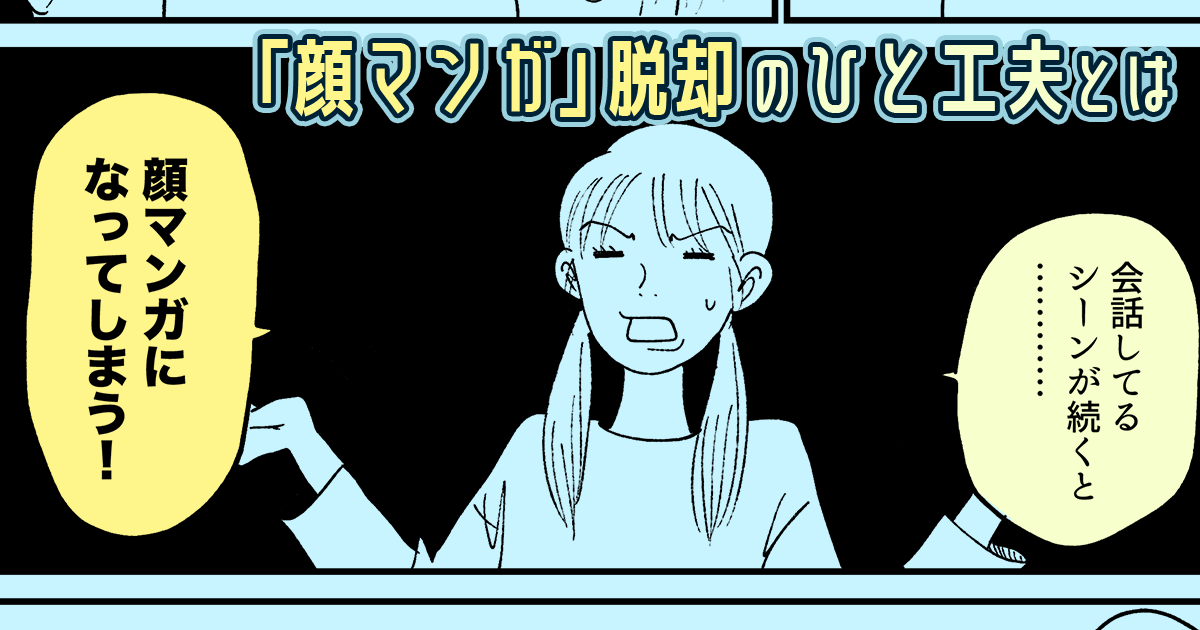「配色と参考資料、仕上げについて」さいとうなおき先生Q&A連載 第2回

こんにちは! GENSEKIマガジン編集部です。
以前の記事でさいとうなおき先生審査員の縛りイラコン「リメイク縛り」講評会をレポートしました。
オンライン講評会では、イラコン応募者のみなさんに質問を募り、さいとう先生にお答えいただくQ&Aの時間がありました。この連載はその内容を再構成し、全3回のQ&A連載としてお届けします!
第1回「キャラデザや構図、イラストの描き方」
第2回「配色と参考資料、仕上げについて」(この記事)
第3回「イラストレーターの活動や仕事について」

さいとうなおき(X:@_NaokiSaito/YouTube)
イラストレーター・ユーチューバー。
1982年生まれ。山形県出身。多摩美術大学卒業後、ゲーム会社を経て現在フリーランス。『ポケモンカードイラストレーター』。
YouTubeチャンネル登録者130万人以上を記録。『お絵描き上達テクニック』などの情報も発信中。
Q.イラストに使う色や色数は、どのように決めていますか?
A.決めるときは資料から。決めないときもあります。
さいとうなおき先生
全然決めていないときと、色のカタログなどを見て5色ぐらい決めているときがあります。色のカタログはKADOKAWAから出ている『写真から見て探せる 配色パターン図鑑』が優秀です。この写真いいな、と思ったらそのカラーパレットから5色ぐらい選んで使いますね。
決めてないときは……流れに身を任せて思いのまま描きます。というのも、「使う色はどう決める? ライティングは? ポージングは?」と玄人になればなるほど考えることになるのですが、そうすると絵を描くのが苦痛になっていくんです。失敗は許されず、業務的になってしまう。そういうのはイヤだなと思って、半分ぐらいは気楽に描いてもいいのかなと思っています。そうすると楽しくできますよ。
Q.安定した基礎的な配色を選ぶクセがあり、サムネイルで映えないと思っています。ベース、アソート、アクセントカラーをどれぐらいの彩度のバランスにすればいいでしょうか?
A.安定していていい。普通に描こう。
さいとうなおき先生
安定した配色でいいです。ですが、こんなに色のことを考えている方なので、もしかすると自分の安定した配色に飽きてきているんじゃないでしょうか? 絵描きを長く続けていると、「奇抜な絵を描かないといけない」と思いがちなのですが、全然そんなことはありません。
大半の人は普通の絵が好きです。サムネ映えしたいというのは、評価されたいということもあると思いますが、普通に絵を描くほうがずっと評価されますよ。

Q.色塗りや下地の色を選ぶのが苦手です。とりあえず薄めの色から選ぶと完成したときの印象が薄くなってしまいます。解決方法を教えて下さい。
A.影を濃くしてみよう。
さいとうなおき先生
薄い色から始めるやり方は間違ってないと思います。ただ、完成した絵が薄い印象になるということなら、影をもう少し強くしてはどうでしょうか。
全体の影を濃くするとコントラストが強すぎるなら、顔のあたりは薄い影で始めて、下にいくにつれグラデーションで濃くなるようにする、など。影の色で解決できると思います。
Q.乗算で塗ると、色のバランスがうまく取れず、全体の色の統一感がなくなってしまいます。乗算の色選びのコツを教えて下さい。
A.色調補正しよう。
さいとうなおき先生
僕も乗算のいい色は一発で選びきれないので、塗ってみて色が違ったら、色調補正でいい感じの色になるまで変えて、その色で塗ります。だいたいのソフトはショートカットの「command+U」(Macの場合。Windowsは「ctrl +U」)で色調補正の機能が出せます。
乗算は下の色に対して色を乗せているので、彩度の高い色などは作りづらいです。もっと澄んだ色にしたいときは、乗算レイヤーの上に通常レイヤーを乗せて塗りなおす、ということもたまにしています。
Q.美しい絵を描きたいあまり加工レイヤーをたくさん使ってしまいます。でも、これでは色の基礎力や描写力が身につかないのではと不安です。解決策はあるでしょうか?
A.ギリギリまで通常レイヤーで描く。
さいとうなおき先生
これは僕も身に覚えがあります。エフェクトや加工など、自分の画力以外の要素で絵を持たせようとしてしまうんですよね。解決策としては、やはりブラシや効果などの偶然性に期待して頼る部分をやめて、色面のベタ塗りだけで描き切る時期を作ってみましょう。
最後まで自分の力だけで描くようにすると、他の人から見たとき明らかに密度が下がって、画力も後退した印象になります。以前に比べて地味に見えるでしょう。僕もやっていた時期はネガティブな意味で「絵柄が変わったね。絵というよりデザインみたい」と言われてしまいました。
でも、自分の中では成長している手ごたえがありました。自分の使いたい色だけでどこまで描けるかをやってみると、色に対する感覚が高まります。
また、ポケモンを描くのもひとつの手です。ポケモンは単純な形でできているので、描いてみると色面構成的な頭が働きやすくなります。練習として最適だと思います。
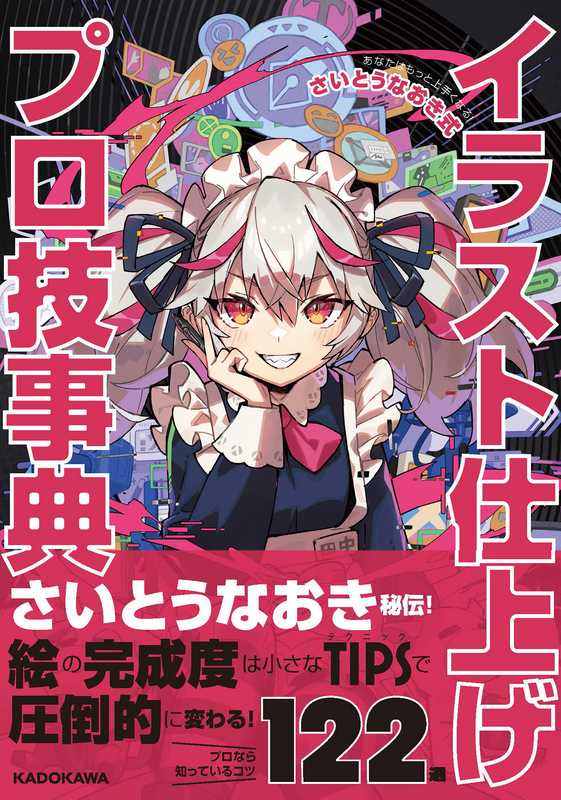
『あなたはもっと上手くなる! さいとうなおき式イラスト仕上げプロ技事典』
Q.吉田誠治さんのようなマットな塗りが好きなのですが、ボヤっと目立たない絵になってしまいます。かといって発光レイヤーを使うとビガビガしてしまいます……。
A.憧れを見て学ぼう。コントラストを恐れず、最後に少しだけ効果を使う。
さいとうなおき先生
憧れている吉田誠治さん(X:@yoshida_seiji)のイラストを見て勉強するのがいちばんです(笑)。それから、コントラスト、明暗の差を恐れずつけましょう。
コントラストをつけるのはけっこう怖いことなので、淡い色からちょっとずつ差をつけていこうとするとボヤっとした絵になりがちです。明暗の差をつけることを怖がらず、明るい色の隣に思い切って暗い色をぶつける気持ちで塗ると、ボヤっとはしなくなると思います。
発光レイヤーは、僕が厚塗りしていたときも使っていました。ただ、仕上げを全部発光レイヤーでやろうとすると、かなりの面積を光らせることになり、ビガビガしてしまいます。
ギリギリまで通常レイヤーでがんばって仕上げて、最後に、例えば肌の光っているところと、光と影の境界で彩度があがるところだけ、発光レイヤーを使うなどがいいんじゃないでしょうか。
Q.絵の仕上げや演出が苦手です。どうしたらこれ以上見栄えがよくなるのかわからなくなり、単にエフェクトを描き加えて終わってしまいます。仕上げはどうやるといいですか?
A.絵の拡大、色トレス、グラデーションマップ。
さいとうなおき先生
ケースバイケースで、完成した絵を見て足りないものを補うのが正しいやりかたです。ただ、方法を一つあげるとすれば絵の拡大が効果的です。多くの人が、キャラを見切れることなく画面内に収めがちです。少し切れてもいいから、大きく配置すると見栄えがよくなります。
僕の場合は、仕上げが好きなのでいろいろやります。まず色トレス(線画を黒以外の色にして絵になじませる)。最近はグラデーションマップです。ちょっと凝ったグラデーションマップをソフトライトで上から重ねて、複雑な感じを出しています。
第1回「キャラデザや構図、イラストの描き方」
第2回「配色と参考資料、仕上げについて」(この記事)
第3回「イラストレーターの活動や仕事について」
縛りイラコン
関連記事
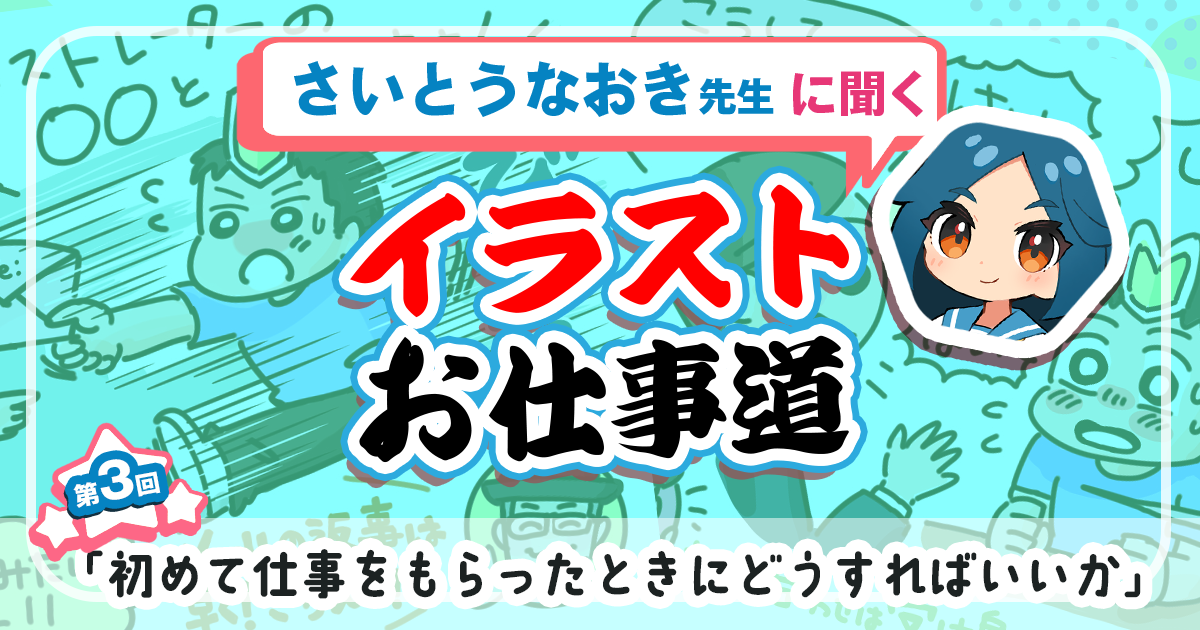

協賛
CLIP STUDIO PAINTは、3,500万人以上が利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。 タブレット、スマートフォン、パソコンといったあらゆるデバイスに対応し、気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。
パソコン工房は、国内工場受注生産のBTO(Build To Order) パソコンや短納期PCの他にも、パソコン自作パーツ、各種周辺機器、組立キット、デジタル雑貨などを販売する全国店舗・WEB通販サイトです。
24時間365日電話サポートと全国店舗展開だから充実したサポートが可能です。
パソコン工房のiiyama PC SENSE∞(センスインフィニティ)シリーズは、動画編集・イラスト制作・写真編集・CG制作・音楽編集など、多種多様なクリエイターニーズにお応えすべく、用途ごとに必要なスペックを検証しております。
クリエイターパソコンをお探しの際は、パソコン工房のSENSE∞シリーズをご覧ください。
執筆
kao(X:@kaosketch/Web/GENSEKI)
この記事を読んだ人におすすめの記事
-
2023.2.16
-
2025.4.8
-
2023.10.12
-
2023.2.28
-
2023.6.22
-
2023.8.16